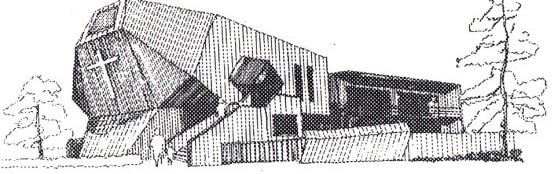「主権」
ここで、1章4~5にしるされているところにあらためて注目してみる。
「神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。」
原初史物語における神の創造行為は第一日から第七日に及ぶが、そのそれぞれに「分ける」が出てき、そして分けた後、そこに分けられた双方のものに「名を付け、その名を呼ぶ」がなされている。
第一日目は「光・闇」を分け、第二日目は「空・海」を分け、第三日目は「陸・海」を分け、第四日目は「太陽・月」を分け、第五日目は「空と海の生き物を種類」に分け、第六日目は「陸の生き物を種類」に分け、さらに人を「男・女」に分け、第七日目は「安息の日とそうではない日」を分け、このように分けた後に、そのそれぞれに「名を付け、その名で呼ぶ」となっている。
原初史物語における神の創造行為の特徴は、「分けること」、分けた後に「名を付け、その名で呼ぶこと」、にあると言ってよい。この神の創造行為の「分ける」と「名付け、その名で呼ぶ」には、重要な意味がこめられているようだ。
この「分ける」「名付け、その名を呼ぶ」、これは神に主権があることを示す。ここで言われていることは、神は地上の全ての存在に関し「主権」を持っている方であるということ、と言ってよい。
ここで、この「神の主権」の内容に立ち入って言うと、神が光と闇を分け、光を昼と名付け、その名で呼ぶということで言われていることは、神は光を創造した方である、光は被造物である、神は被造物である光に昼という役割を与えその役割に定めた、こういうことである。このことは当時の宗教的文化的状況を考慮するとき、重要なことが言われていることに気付かされる。
当時すなわち古代オリエントの時代とその世界では、「光」は全ての物を「創造する神」である。このことは当時の宗教・哲学・自然科学の公分母であった。しかし、この古代オリエントの環境の中で創世記の原初史物語を生んだイスラエルの民は、そうは考えなかった。この民によれば、「光」は「神」ではなく「被造物」であり、それは「昼」という役割に限定された存在である。
ここで、この原初史物語作者の言うところを思想として言えば、全てのものを相対化し、相対化した中でそれぞれの特性を認めるとする、つまり地の存在の間に支配と被支配の関係をきたらせない、それぞれの特性を相対化の中で認める自由な精神、こう言ってよいとおもう。
原初史物語の作者がこのような自由な精神を持ち得たのは、「主権」を「人」の側に置かず、「神」の側に置くがゆえであったと推測される。
ここで注意しておきたいことがある。ここで原初史物語の作者は、神は主権をもって分け、分けたその個々に名を付けその名で呼び、その分けられた個々にそれぞれの役割を与える主権者であるとするが、これを超越的主権者によって定められた運命・宿命という考えに傾斜させてはならないということである。ここは「抵抗の論理」として語られたものとして解されなければならない。
原初史物語の作者は今バビロンに捕囚となり、バビロニア国家の被支配民となっている。国家当局は国家の価値基準に従ってその被支配民を分け階層化し、それぞれに国家の側から名を与え、国家主権としてそのそれぞれに役割を与える。原初史物語の作者はこういった国家支配の中に置かれていた。
原初史物語の作者は、このような国家の側からの「分ける」と「名を付ける」に対する抵抗として、「主権」は「神にあって国家にはない」と語った、とおもわれる。ただ、このような抵抗をあからさまに示すことは生命の途絶危険を意味するゆえ暗喩を用いた。すなわち、「天地創造物語」に託して暗々裏に語った。
ところで、原初史物語の作者によれば、「神は光と闇を分けた」後、その「闇を夜と呼んだ」とあり、これは神が闇に夜という名を与え、その役割を与えたということを意味しているが、このことについて、わたくしは読者の一人として疑問なしではない。
原初史物語の作者はここで、神は「闇」に「夜」という名を与えその役割を与えたとし、神はその仕方で「闇」を「夜」の時間に限定し神の主権の下に置いたと語るのだが、しかし「闇」は神の創造した世界を混乱させ荒廃させ退廃させる動因であり、したがって「闇」はなくしてしまうべきものであると考えるのが普通のことではないかとおもう。
しかし、原初史物語の作者は、神は「闇」を「夜」の時間に限定し神の主権の下に置くという仕方で「闇」を存続させたと語る。ここで、これはいったいどういうことかと疑問が生じる。
この疑問に対し原初史物語の作者はこう応じるのではないか、と推測される。
地の世界には「闇」が支配する「夜」の時間がある、しかし「闇」は「夜」の時間だけに限定されている、「夜」が明ければ「闇」の支配の時間がなくなる、しかし「闇」の支配する「夜」の時間はやってくる、わたしたちには「闇」がまったくない世界や時間はない、「光」だけがあり、「昼」の時間だけがあるということはない、わたしたちはいわばこのような「緊張した」時間と世界、この中で生きる、これへと招かれている。原初史物語の作者はこう語るのではないか。