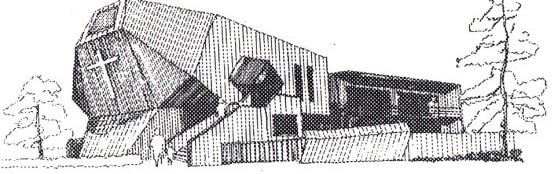「人間の創造」
2章4後半から新しい物語が始まる。その新しい物語の初めにしるされているのは〈人間の創造〉である。
2章7
「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、」
〈人間は土で造られた〉とある。この文章はこの後に語られる物語のために敷かれた伏線であるとおもわれる。
この後に語られていることは人間が〈神のようになる〉ことへの誘いであるが、物語作者がそれを語るとき、その〈神のようになる〉とは人間が〈土で造られた〉ことを棄却すること、それを言おうとしていると言ってよい。物語作者はそれを語るために伏線を敷いた、それが2章7の〈人間は土で造られた〉である。
物語作者はこの後の三章の物語において、〈神のようになる〉ことへと向かっていった人間に起こったことは〈自分の裸を恥じる〉ということであったと語るが、その〈自分の裸を恥じる〉ということは〈土で造られたことを恥じる〉ということ、それを言おうとしている。物語作者はそれを語るために伏線を敷いた、それが二章七の〈人間は土で造られた〉である。
物語作者は、人間が〈神のようになる〉ことに向かってゆくことによって〈土で造られたことを恥じる〉ことになった、それが人間をいかに悲惨な結末へと至らせるかについて語る。(このことについて詳しくは後で。)
さて、物語作者は人間が創造されるとき、地がいかなる状況にあったかを描く。
2章5
「地上にはまだ野の木も、野の草も生えていなかった。」
ここに描かれている地の状況は次のように言い換えることができるのではないか。すなわち、〈地は食べ物を産み出す状況になっていなかった〉。
この2章5にはさらに「土を耕す人もいなかった」としるされている。
そうすると、ここに描かれているのは、〈人間が創造されたとき地は食べ物を産み出す状況にはなかった、人間はその状況の中で創造された、人間は土が食べ物を産み出すべく土に仕えるために創造された〉ということであるとおもう。
ここで、こう語る物語作者の意図をおしはかっておきたい。
この物語が書かれたのはダビデからソロモンの時代でありその社会においてであったとおもわれる。この時代と社会は今日の言葉で言えば「格差」を生じさせていた。
この時代と社会は〈独立自営農民〉が消滅してゆく状況にあった。大きな農園を所有する富んだ者たちが〈独立自営農民〉としてやってゆけなくなった者たちを〈農奴〉として雇い、また農園を防衛する〈兵士〉として雇うという状況にあった。つまり、この時代と社会においては〈土に仕える〉のは大農園の〈農奴〉だけであり、大農園を所有する富んだ者たちは〈土に仕える〉ことをしていないという状況にあった。
原初史物語の作者は〈人間の創造〉の物語において〈人間は土が食べ物を産み出すべく土に仕えるために創造された〉と語ったが、物語作者の語るこの〈人間の創造〉の物語において言われている〈人間〉とは〈全ての人間〉であるということ。そうすると、この〈人間の創造〉の物語において語られていることは〈土に仕える〉のは〈全ての人間〉であるということである。
物語作者はこの〈人間の創造〉物語にことよせ、この物語に忍ばせてこの時代と社会の状況に対する批判を、すなわち〈土に仕える〉のは〈農奴〉だけであって、大農園を所有する富んだ者たちは〈土に仕える〉ことをしていない状況に対する批判を展開した、と、わたくしには読める。
物語作者が時代と社会に対する状況批判を展開した方法が〈人間の創造〉の物語にことよせ、物語に忍ばせるという方法であったのは、批判をあからさまにすることはできない、それをすれば命を奪われかねない状況にあったからである。しかし、黙し見逃していることはできない。とすれば、採用し得る批判方法は〈隠喩〉によるということになる。物語作者はそれをおこなった、と、わたくしは読む。
ここで、〈土で造られたことを恥じる〉、このことについて考えておきたい。
3章にしるされている物語は〈善と悪を知る知識の木〉の実を食べた結果人間は〈自分の裸を恥じる〉に至ったと語る。この〈自分の裸を恥じる〉とは〈土で造られたことを恥じる〉ということであった。この〈土で造られたことを恥じる〉とは土の性質である〈もろい〉〈よわい〉を恥じるということであった。三章にしるされている物語はこう語っているのであるが、ここには問題の提起があるとおもわれる。はたして〈もろい〉〈よわい〉は恥ずべきことであるのか。むしろ、それの逆の〈強い〉ことのほうが恥ずべきことをおこなうことになるのではないのか。
人間が〈強い〉とき〈権力〉を持つことになるのであるが、そのとき人間は他者を支配する、抑圧する、虐待する、抹殺さえする、それが可能になるときであるということではないか。これは人間が恥ずべきことをする可能性にあるということではないか。このような恥ずべきことをする可能性にあることにならないためには、人間は〈強い〉ものにならないほうがよいのではないか。
これとは逆に人間は〈もろい〉〈よわい〉とき、〈強い〉が持つ可能性の恥ずべきことから遠くにいることができる。遠くにいることができることによって〈共に生きる〉ことの可能性が開かれてくる。なぜなら、〈できない〉ことが許せるようになる、〈できない〉自分を許し、また〈できない〉他者を受け入れることが起こるようになるからである。
3章にしるされている物語によれば、人間は〈善と悪を知る知識の木〉の実を食べると、この〈もろい〉〈よわい〉の持つ良さを失うことになる(詳しくは後で)。
次に注目するのは〈土で造られた人間〉に対して神がなさった次のことである。
2章7
「主なる神は、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。」
主なる神によって〈吹き入れられた命の息〉は〈神の霊〉のことを言っているとおもわれる。ここで考えておきたいことは、物語が人間とは〈神の霊〉を持つ存在であるとしている、そのことについてである。
このことについて示唆を与えられたのは、カール・バルトの『教会教義学』の中の次の文章である(わたくしの要約で紹介する)。
創世記2章7には、人間には神から命の息が吹き入れられたとあり、これは人間が〈神の霊〉を与えられている存在であることを示している。ここにはヘブライ人の人間理解が示されている。すなわち、人間には神の霊(息)が与えられ、それゆえ人間は神と向き合い、神の意思を問いかつ聴く可能性を与えられている。このヘブライ人の人間理解はギリシャ人のそれと比べてみると、その特徴がはっきりする。
ギリシャ人の人間理解は〈人間は肉体を持ち精神を持つ〉とする。このギリシャ人の人間理解によれば、精神のはたらきのゆえに、人間は自分を見つめることができ、自分を分析することができ、自分と自分との関係を探り定めることができ、また他者を観察し、分析し、他者と向き合い、他者との関係を探り定めることができる。
ヘブライ人の人間理解もギリシャ人の人間理解と同様に、精神のはたらきを持つ。すなわち、人間は自分を見つめることができ、自分を分析することができ、自分と自分との関係を探り定めることができ、また他者を観察し、分析し、他者と向き合い、他者との関係を探り定めることができる。しかし、次の点で異なっている。すなわち、
ヘブライ人の人間理解による人間は神の霊が与えられ、人間は神と向き合い、神の意思を問いかつ聴く可能性が与えられている。これはギリシャ人の人間理解の人間が〈肉体・精神〉の二元構造であるのに対し、ヘブライ人の人間理解の人間は〈肉体・精神・霊〉の三元構造であることを示している。
ギリシャ人の人間理解は人間が人間と向き合うという構造であるが、ヘブラ
イ人の人間理解は人間が人間と向き合うという構造と共に、人間が神に向き合うという構造が存する。
バルトはこのように述べている。彼は聖書の示す人間理解を〈ヘブライ人の人間理解〉と呼び、その特徴を浮き彫りにするため〈ギリシャ人の人間理解〉に対照させた。このバルトの論述は聖書の示す人間理解をとらえるうえで良き道案内になるとおもわれる。
ところで、創世記の原初史物語の作者は〈人間には神の霊が与えられている〉と語ったが、ここでも物語作者は時代と社会に対する批判を意図していたのではないかとおもわれる。
ダビデからソロモンの時代と社会において体制は神の意思を問いかつ聴く預言者を側に置いていた。このことは〈人間には神の霊が与えられている〉〈人間は神に向き合い、神にその意思を問いかつ聴く〉この人間理解を保持していたことを示しているのだが、しかし、実質的にはその人間理解を棄てていたと言わざるを得ない。というのは、この体制が側に置いていた預言者は体制を肯定し支持するだけの存在であり、体制とは距離を置きそれとは独立して神の意思を問いかつ聴く預言者ではなかったからである。
体制と距離を置きそれとは独立して神の意思を問いかつ聴く預言者が不在であるというこのことは、これまで共有してきた人間理解を消失させてしまっていたということ、すなわち人間には神の霊が与えられており、人間は神に向き合い、神にその意思を問いかつ聴く可能性の中にある存在であるとする人間理解を消失させてしまっていたということ、それを示していると言わざるを得ない。
このゆえに生じたことであったとさえ言ってよいのだが、体制の権力を握った者たちは自己を相対化することができなくなり、自己を絶対化し、権力の横暴をきたらせ、それを止めることができなくなっていった。
創世記の原初史物語の作者は人間とは何であるかについて語った、すなわち〈人間とは神の霊が与えられている存在である〉と語ったが、この語りはただ単なる人間論の提示ではなかった。この語りはダビデからソロモンに至る時代と社会の体制における根本問題に切り込む語りであった。
原初史物語作者のこの語りは神にその意思を問いかつ聴く可能性の中にある人間であることを棄却することによって自己を相対化することができなくなり、自己を絶対化し、それを止めることができなくなっていった、その根本原因に切り込む語りであった、と、わたくしは読む。