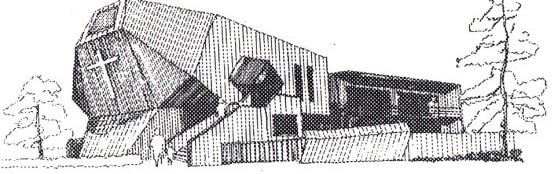「安息の創造」
2章1~4前半
「天地万物は完成された。この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。これが天地創造の由来である。」
原初史物語は創世記1章1から2章4前半までがひとまとまりの物語となっている。ここ2章1~4前半はその結びとなっている。ここには「安息の創造」がしるされている。この「安息の創造」が1章1から2章4前半のひとまとまりの物語を締め括る結びとなっている。
ここで、「安息の創造」が天と地の創造物語の結びである、それはなにゆえであるか、原初史物語作者の意図するところをとらえておきたい。
原初史物語作者は、神は安息を創造した、安息の創造があって天と地の創造は完結した、神は安息を全ての生きとし生けるものに与えた、と語った。この語りは、実は捕囚民の安息要求であったと言ってよいのではないか。
創世記の原初史物語作者はバビロン捕囚の中にある。この捕囚状況の中で失っていた最たるものは「安息」であった。捕囚民は安息のない状況にあった。捕囚民が最も切実に求めていたものは安息であった。
捕囚民が安息の要求を直接言うことは捕囚民の生命の途絶の危機を招来させる。それゆえ、安息は神の天と地の創造の完成として創造されたと、つまり暗喩によって安息の要求をした。ここはこう読んでよいのではないかとおもう。
ここで、この「安息」ということについて考えておきたい。
この「安息」は原初史物語作者を含むイスラエルの民にとって、根源的理由において、なくてはならないものである。というのは、この民は安息を求めたところにこの民の成立の始原があるからである。
この民は苦役からの解放すなわち安息を求めたことによって成り立った民であるゆえ、安息はこの民にとって根源的理由でなくてはならないものであった。この民は「安息」を求めて生まれたのであり、これを失うということは、この民の全的否定となる。こう言ってよい。
出エジプト記のしるすところによると、モーセはエジプトの権力者皇帝ファラオに苦役を強いられているへブライ人たちの安息を要求する。ファラオはこの安息の要求を拒否。モーセは重ねて要求。しかし、ファラオは拒否。モーセはエジプト脱出を決行。この民はこの始まりのゆえに、「安息」を最も重要なものとしてゆくこととなった。
この民は安息が最も重要なものであることを知った民、安息が最も重要であると言い続ける使命にある民である。それゆえ、安息を喪失せしめられているバビロン捕囚はこの民を全的に崩壊させる事態であった。
「安息日を守る」ことはバビロン捕囚よりも前に始まっていたが、「安息日を守る」が最も重要なこととなったのは、安息を喪失せしめられたバビロン捕囚の時であった。この時、「安息日を守る」にこの民の命運がかかっていた。
原初史物語作者は神による天と地の創造物語の結びで「安息の創造」を神がおこなったと語った。この語りはこの民の命運がかかるものについての語りであった、と言ってよい。
古代オリエント社会において社会の上層の特権階級にある者たちは安楽に暮らし安息を得ていたが、下層民たちの日々は苦役を強いられ安息はなかった。捕囚民のイスラエルの民たちも同様の状況にあったろう。
この状況の中で、捕囚民となっていたイスラエルの民は自分たちの自分たちであることを確保するために安息日の要求をしていった。六日の後に一日を安息の日として要求する、このことに極めて大きな困難が伴っていたことは想像するまでもない。この民はその困難状況の中で、六日の後の一日を安息の日とすることを要求し、この意志を貫き続ける。おどろくほかない。
ここで、出エジプト記20章に安息日のことがしるされている、そこのところを読んでおこう。
「七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしては
ならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。」(出エジプト記20章10)
ここには、男女の奴隷も、寄留の外国人も、全ての人々が安息を得ることができるとあり、また家畜においても、六日の後の一日は休ませなければならないとある。
興味深いことに、レビ記にしるされているのだが、安息が与えられるのは生きものだけではなく、土地(畑)にも安息が及ぶとされ、「七年目には全き安息を土地に与えねばならない。」(レビ記25章4)とある。六年間は種を撒いて耕作をするけれども、七年目は一年間、畑に安息を与えなければならない。
出エジプト記20章の記述は、安息は全てのものたちに与えられ、安息は子々孫々にわたって引き継がれるべきものとしているが、この記述には次の意味合いがこめられていたのではないか。すなわち、安息を確保することは極めて至難であった、もし失ったら再び得ることは極めて困難、いや、できないだろう、それゆえ、安息の定めはなんとしてでも継承されるべきものである。
この民は安息を求め続け、安息を確保し、安息を子々孫々にわたって引き継がれるべきものとしたが、この民のこの歩みは人類史に極めて大きな貢献をなしたと言ってよい。
ここで、キリスト教神学者ユルゲン・モルトマンの述べるところを紹介する。
近代から現代において、工業文明の中で、人々は皆、同じ洗礼を受けてしまった。「進歩、前進がよいものだ」という教えの洗礼を受けてしまった。前に進むことが美徳であり、休むことは非道徳的であるとした。近、現代において、人々は、ひとつのことを忘れた。安息ということの意義を忘れてしまった。これが、工業文明の中にいる人間の一般的傾向となった。ここに、現代人が競争しか考えない、共に生きる平和を持たない原因がある。
近、現代という時代は、科学工業の分野において、また経済の分野において、進歩・前進・進化ということが良いものだという前提を信じて疑わない時代であった。これに共通するのは、「安息」というものが持っている意義を忘れてしまったことである。
もし、このまま進歩、前進、進化という精神性を信じて疑わない人々がこの地球の歴史を動かしていくなら、すなわち安息の意義を知らない人々によってこの世界が動かされていくなら、この地球の消滅は時間の問題であると言わなければならない。
このことを考えると、安息という思想をもたらしたヘブライ思想は人類の歴史に極めて大きな貢献をした、最良のプレゼントをした、と言ってよい。
ここで、今日のこの国の哲学者、鷲田清一の述べるところを紹介する。ここでは鷲田の著書『老いの空白』に述べられているところを紹介する。そこに述べられていることは、「安息」の問題に関わるとおもわれる。
「老い」が無用な「お荷物」で、その最終場面では「介護」の対象として意識されるという惨めな存在であるかのようにみなされるに至ったのは、生産と成長を基軸にする産業社会の価値観が支配的となったことによる。生産性・効率性・有用性・合理性を軸とする社会の中では「無用」の烙印を押され、せいぜいのところ「補完」や「許容」の対象として位置づけられるに至った。
「老い」ということは産業社会の価値基準が支配的な中では「できる」存在から「できない」存在へと移転させられることである。が、この「できない」存在に移転させられることによって分かってくることがある。それは、「できない」ということは「産業社会の価値基準」においてであるにすぎないということ、人間は「産業社会の価値基準」で価値を判断される必要はないということ、が分かってくる。
この「できる」と「できない」という言い方は「する」と「ある」という言い方で扱い得る。「老い」は産業社会の価値基準が支配的な中では「する」存在から「ある」だけの存在へと移転させられる。が、この「ある」だけの存在に移転させられることによって分かってくることがある。
それは、人間は「する」という観点からだけみることは正しくなく、むしろ人間は「ある」という観点からみるとき人間の本来性をとらえることができる。すなわち、人間の本来は「いるだけでいい」「あるだけでいい」存在である。人間は「老い」に至ってこの人間の本来を見出すことになる。
この哲学者鷲田清一の述べるところは「安息」の問題に関わるものである。この哲学者は人間の本来は「いるだけでいい」「あるだけでいい」存在であると述べるが、これは「人間の安息」に関わることと言い換えることができる。
この哲学者鷲田清一の述べるところは、最初期キリスト教のパウロの語りと重なる。パウロは言った、「人が義とされるのは行いによるのではない、ただ神の恵みによる義認によってである。」
このパウロの語りはキリスト教の教理の中軸となっていったが、このパウロの語りはこう言い換えることができる。人が生かされるのは「できる」においてではない、「する」においてではない、そうではなく「できない」において、「ある」においてである。人は「いるだけでよい」、人は「あるだけでよい」。パウロの言う「ただ恵みによる義認」は「安息」について語るものと言い換えることができる。
ここで、キリスト教神学者のカール・バルトが『教会教義学』において「安息」の重要性について述べているところを紹介する。
安息の創造は神の創造の業の最終のものであった。しかし、人にとっては第一日目に当たる。人にとって最初の日は安息の日であり、人の生活は安息することから始まる。人の生は安息することから始まり、安息することへと戻る、そして人の生は安息することから始まる。
人の生活は安息することで、これまで続けてきた生活を中断することになる。そうすることで人は仕事から自由になり、自分自身から解放される。人は自分の主張をいったん中断し、他者に向き合い、他者の思いに心を向けることができる。
この安息による中断の時は、人は自分を創造した方に心を向ける時である。そうすることで、人は自分を問い直し、自分の軌道を直すことができる。そうすることで人は人として人らしく生きることができる。
神が安息を第七日目に創造した、そのことによって人の生活が安息から始まるということになったということ、このことには神の創造における深い配慮がある。
ここで、「安息」の問題を別の観点からみてみることにする。旧約聖書学者のフォン・ラートの述べるところを紹介する。
イスラエルの民は神を像の形で表すということをしなかった。像、形において神と出会うことはできないとした。それでは神との出会いをどこに求めたか。この民は時間の中に求めた。すなわち「安息日」という時間の中に神との出会いを求めた。この時間の中においてこそ神と出会うとした。神との出会いを像とか形においてできる場合は人間が自分の都合のよい時間に神に出会いに行くことになる。これに対して安息日という特定の時間において神と出会うことができるとする場合は人間が自分のことを中止してその時間に向かうことになる。この民はこの生き方を選んだ。
創世記の安息に関するところも素材を古代オリエントのバビロニア神話から得ているが、その内容を比べてみてみると決定的な違いがある。バビロニア神話では天地創造が完成した最終日に、マルドウクという最も強い神が登場し、そこに催された神々の集会において褒めそやされるという光景が描かれている。それに対し創世記の原初史物語にあっては、天と地の創造の完成の最終日には「神は安息した」のであった。この違いは両者を決定的に違うものとして示している。
このフォン・ラートの指摘するところは、創世記の原初史物語作者の「神は安息を創造した」にこめた物語意図を理解するうえで重要である。
物語素材としているバビロニア神話では、天地創造の神マルドウクの自分の業への讃美に酔いしれている姿が描かれているが、創世記の原初史物語作者は、自分たちの信じる神はそれをしない、ただ静かに安息する神であると語った。
この原初史物語の語りは次のことを示しているとおもわれる。原初史物語の作者はここで、王ソロモンが自分の業績に対する称賛を要求し、その称賛の言葉に酔いしれている、また、権力にある者たちが自分の業績に対する称賛を要求し、その称賛の言葉に酔いしれている、それを愚かしいこととして示した、とおもわれる。この原初史物語の語りは今日においても通用する。
ここで、宗教社会学者マックス・ヴェーバーが『古代ユダヤ教』の中で述べているところを紹介する。
イスラエルという客人民族の地位は儀礼的遮断によって基礎づけられた。とくにバビロン捕囚期には安息日の厳格な聖化が最も重要な儀礼的識別のための命令の一つとして前面に押し出された。安息日の厳格な遵守による儀礼的遮断によってイスラエルはその存在の独自性を基礎づけ、保持することができた。これがなければ、イスラエルはバビロニア帝国の同化政策に呑みこまれ、無となっていたであろう。
このヴェーバーの指摘は、原初史物語作者が「神は安息を創造した」にこめた物語意図を理解するうえで重要である。
原初史物語作者のイスラエルの民はバビロン捕囚の中で少数者であって、多数者のバビロニア帝国による同化政策の中で無となるほかなかった。この民はこの事態の中で独自性を自覚し確保するため、同化に抵抗するために「安息日の遵守」を敢行した。
この「安息日遵守」の敢行がいかに至難のことであったかを知りぬいていた原初史物語作者はここで、「安息日遵守」の根拠を語った。すなわち、「神は安息を創造した」を「天と地の創造物語」の結びとして語り、「安息日の遵守」の根拠を提示した。
原初史物語作者の「天と地の創造物語」の結びとしての「神は安息日を創造した」この語りは、この民の独自性の自覚と確保のため、同化に対する抵抗のための根拠を提示したものと言ってよい。原初史物語作者の「神は安息を創造した」の語りの背後には同化に対する抵抗のたたかいの生があったとみてよい。
わたしたち読者は原初史物語作者の「神は安息を創造した」の語りの背後に同化に対し、それを拒む抵抗のたたかい、それがあったということを記憶し覚えたい。
この「安息」に関する項目で終わりに言及しておきたいのは次のことである。それは最初期キリスト教の人々が安息日を変更したことについてである。
ユダヤ教では安息日は金曜日の午後六時から土曜日の午後六時であったが、最初期キリスト教の人々は、翌日の日曜日を安息日にした。この変更の理由であるが、ユダヤ教安息日の翌日の日曜日にイエスの遺体の無い空虚な墓の発見があり、「イエスは復活した」の信仰が生起した、そこにその理由があると推定される。
最初期キリスト教の人々はほとんどがユダヤ教徒であったから、安息日を変えるということはよほどのことがない限りできなかったことと言ってよい。したがって、この変更の背後には、「よほどのことが起こった」とする信仰があったとみるほかない。
この世の権力によって蹂躙され抹殺されたイエスを神は復活せしめた。この復活は神の勝利。この神の勝利を祝おうではないか。
最初期キリスト教の人々はこう考えて、安息日を土曜日から日曜日に変えたのであろうとおもわれる。
テキストはここへ