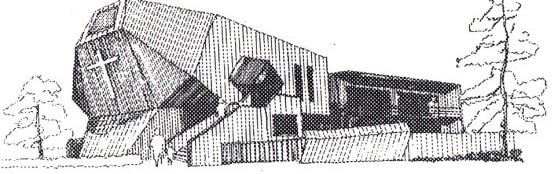マルコ福音書から(37)15章21~32 《自助の思想を棄てよ》
物語はイエスの最期の姿を描く。
そこには十字架につけられたイエスに対する人々の嘲笑と罵倒の言葉が記されている。
「『十字架から降りて自分を救ってみろ。』同じように、祭司長たちも律法学者
たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱して言った。『他人は救った
のに、自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りる
がいい。それを見たら、信じてやろう。』」
ここには、他人を救ったのに自分は救えない、自分を救えず自分を救わない、そういうイエスが描かれている。
ここに登場する人々は多種多様の人々であり、立場の全く異なる人々であったのだが、興味深いことに、共通の価値観を持っている。それは、この人々の言葉に即して言うと、「まず自分を救え」という価値観である。
この物語場面、人々は自分たちが持っている価値観を信じ切っているように見える。
「まず自分を救え」それが先だ、この価値観の正しさを信じ切っているように見える。
しかし、わたくしは、この人々には信じ切っているにしてはそれにふさわしくないものが感じられる。この人々の心に不安が存在していたのではないかという印象を受ける。
ここに登場している人々は「まず自分を救え」を価値観の最上位に置いている人々であるが、しかし、そうであったのであれば、人々はイエスを冷ややかに見ているだけであったのではないか。しかし、この場面に描かれている人々のようすは興奮しており、憎悪の感情をむき出しにしてイエスに罵倒の言葉を浴びせている。これはどうしたことであろうか。
わたくしの推量では、人々はここで自分たちの生き方とはあまりにも違う生き方をするイエスの姿を見て、すなわち「自分を救わない」イエスの姿を見て、自分たちの精神の奥深くにある自分たちの価値観「まず自分を救え」に対し、「はたしてこれでいいのか」という不安、それがここでうずいたのではないだろうか。
ここに登場した人々が信じ切っていた価値観「まず自分を救え」この価値観は「人間は自分を救うことができる」という前提に立った価値観と言えよう。この価値観は別言すれば、知恵」という人間能力に頼る価値観であると言えよう。
ここで、きょうの福音書物語を今日の事として受け取るために、一人の哲学者の名を挙げ、その思想をみておきたい。ここでその名を挙げるのは、デカルトである。
わたくしの考えるところ、きょうの福音書物語に登場する人々の価値観を今日の事として受け取るためには、デカルトの思想をこれに照らし合わせてみると、益することになるのではないかと思う
ここで、デカルトの思想を一言で言ってみるが、わたくしの言い方ではこうなる。
人間とは何者であるか。それは疑うことができるということ。人間は疑う能力を持っている。疑うということのできる能力が人間の知恵である。デカルトの言うところを一言で言うとこのようになるかと思う。
このデカルトが人間精神にもたらした貢献はあらためて言うまでもない、その歴史的意義はきわめて大きい。しかし、問題があったことを知っておかなければならない。
デカルトは、人間は疑うことのできる能力を持っており、どんなものをも疑うことができるできとしたが、しかし、ただ一つ疑えないものがあるとした。それは疑ってい
る私自身を疑うことはできない。なぜなら、この疑っている私自身を疑ってしまったら、疑うことをしている私が否定され、疑うということが成り立たなくなり、全てが終わってしまう。それゆえ、疑っている私は疑えない、と、このようにデカルトは言った。
このデカルトの言うところに大きな問題が潜んでいた。
疑っている私は疑えないとするところから立ち現われてきたのは、自分の獲得した知恵に自信を持った人間である。ここから自分で自分を救うことができるとする考え方が勢いよく走り始めた。人間は自分の知恵によって自分を救うことができるという信念が揺るぎのないものになっていった。
このデカルトの哲学を、わたくしは「自助の思想」と言っておきたい。
人間は人間以外のものからの助けを必要とせず、全て自分でできる。したがって神からの助けは必要ない、動物や植物などからの助けも必要ない。必要のあるときは、神であれ、動物であれ、植物であれ、それらのものは人間のための手段として使えばよい。
わたくしは、このデカルトの哲学に潜む問題を次の書から学んだ。
それは、カール・バルトの『教会教義学』という書からである。
ここで、この書から教示されたことについて述べてみることにする。
バルトはデカルトの言うところを詳細に紹介する、そのうえで批判を述べる。
デカルトは疑うことに人間であることの確認を行った。このデカルトの命題は正しい。ただ、このデカルトの命題が正しくあるためには、全てのことを疑うということがなされなければならない。しかし、デカルトは、疑っている私を疑うことはできないとした。
これではデカルトの哲学は完全なものにならない。残念なことにデカルトはそれができなかった。
実は、疑っている私を疑うことは出来ないとしたところから、人間の知恵の自己絶対化が起こっていった。この自己絶対化にひた走る人間に待ったをかける、これを止める思想が必要である。その思想は疑っている私を疑うことができる思想である。それができる思想はいったい何処にあるのか。バルトは言う、それは人間の外に求めるほかない。
ここで、バルトの述べる結論を端的に言うことにするが、彼によれば、私を疑うことのできる思想は聖書にある。
わたくしはこのように述べるバルトから深い示唆を与えられてきた者の一人である。
きょうのマルコ福音書の物語に登場している人々は自分を救えず自分を救わないイエスに対し、それでメシアであると言えるか、自分を救うことを示してこそメシアであるとする人々であるが、極めて興味深いことであるが、この人々は近代の人間の中に現われているのではないか、ということである。
デカルトから始まった近代の人間は、自分を救うことに自信を持ったがゆえに、きょうのマルコ福音書の物語に登場する人々がするように、「自分を救えず自分を救わない」イエスを嘲笑する人間となっている、こう言ってよいのではないか。
ここで、わたくしの読みを言うと、こうなる。
きょうのマルコ福音書物語は「自助の思想」を棄てたイエスを描くのだが、この物語はこのイエスに真理が隠されているとしている、と、わたくしに思われる。
では、この「自助の思想」を捨てたイエスに、いかなる真理が隠されていると言えるのか。
人間の歴史は、自分で自分を救うことに自信を持つ者たちが現れてはこの世界を救うどころか世界を破壊する。知恵に自信を持った者がこの世界を生存の危機に至らしめる。
決まってそうであると言っても決して言い過ぎてはいない。
そうであるゆえ、人間の歴史が破滅の恐怖から解放されるためには、人間が「自助の思想」を棄てること、そこから始めなければならない。
きょうのマルコ福音書の物語はこの人間歴史の現実に対し問題提起している。
自分で自分を救うことができるとしている者たちに対し、それでいくとこの世界は破滅する、その「自助の思想」を棄てよ、と、きょうの福音書の物語は問題提起している。と、わたくしには思われる。
イエスが生の最期になさったことは「自助の思想」を棄てた姿を提示することであった。と、わたくしには思われる。
最期のイエスは、自己を義認するだけで「自助の思想」しか持たない者たちの嘲笑と罵倒を浴びせられたが、その中で、「自助の思想」を棄てることに真理があることを提示した。と、わたくしには思われる。
マルコ福音書が書かれたのは二千年前。この書はこの遥かなる時間を越えて今日のわたしたちに問題提起する。生きた書というのは、こういう書のことだと思う。