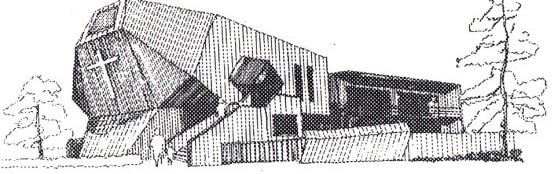「共同・共生の人間」
原初史物語の作者は、〈エデンの園〉における人間は〈地に仕える〉人間であるとしるしたが、この人間は〈共同・共生〉に生きる存在であるとしるす。そこのところも丁寧に読んでみよう。
2章18
「主なる神は言われた。『人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。』」
ここには原初史物語作者の人間理解が言い表されている。〈人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう〉の表現からして言い得ることは、神ヤハウェによって創造された人間とは〈共同性〉〈共生性〉を持つ存在であるということである。
原初史物語作者は、人間の持つ〈共同性〉〈共生性〉について、すでにしるしていて、こう述べている。すなわち、人間は〈土〉から造られ〈土との共同性・共生性を持つ存在〉である。この〈土との共同性・共生性〉、このことは原初史物語作者が強調点を置いて述べるところであるので、ここでいまいちど確認しておきたい。
原初史物語の作者が〈人は土との共同性・共生性を持つ〉というところに特別の強調点を置いていることについては、この後にしるされる四章からの物語において明らかになる。そこには〈土〉が〈食べ物〉を産み出さなくなるということがしるされている。
4章12
「土を耕しても土は作物を産み出すことはない。」
これは〈土〉と〈人〉との共同・共生が失われるということを意味する。〈土〉が人の命を養い支える〈食べ物〉を産み出さないということは〈土〉と〈人〉との共同・共生が失われるということにほかならないからである。
〈土〉と〈人〉との共同・共生が失われる原因は人が人の命を奪い殺したことにあるが、そのとき人は4章12にしるされているが「地上をさまよい、さすらう者となる」。この〈地上をさまよい、さすらう〉の意味するところは〈土から離れる〉言い換えれば〈土〉と〈人〉との共同・共生が失われるということであると言ってよい。
原初史物語の作者は〈土〉と〈人〉との共同・共生が失われることが深刻な事態(土が人の命を養い支える食べ物を産まないという深刻な事態)を生むということをこのように述べているが、これは〈土〉と〈人〉との共同・共生に特別の強調点を置いているということを意味していると言ってよい。
ところで、物語作者はこの人間の持つ共同性・共生性の別な面について語る。
2章19~20
「主なる神は、野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形づくり、人のところへ持って来て、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて、生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名を付けたが、自分に合う助ける者は見つけることができなかった。」
ここには「人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名を付けたが、自分にう助ける者は見つけることができなかった」とある。ということは、人間は共同性・共生性を神ヤハウェが創造した〈動物〉の中に求めた、ということがここで言われていることになる。ここは興味深いところである。ここで、そこを少しばかり散策してみることにする。
人間と動物との共同・共生がなくなってゆくということが起こる。それは〈農的環境〉が消えてゆく中で、つまり〈都市化〉において起こる。この〈都市化〉が著しく生じたのはダビデの後のソロモン王政においてであるようだ。ソロモン王朝の政策は〈都市化〉を著しく生じさせたようである。この〈都市化〉は動物との共同・共生の農的環境を消えさせる。ソロモン王政の時代、これが著しく生じたことがソロモン王政について詳しく述べている列王記上の記述から推測できる。
創世記の原初史物語の作者はここで、人間は共同性・共生性を確認する対象相手をまずは動物に求めたと語るのであるが、この語りはもしかすると、次のようなことであったのかもしれない。すなわち、原初史物語の作者はこの〈都市化〉状況に危機意識を持っていた、この〈都市化〉状況が進めば人間がいるだけの世界となり、動物との共同・共生が消滅する、この〈都市化〉状況は共同性・共生性を持つ人間にとって危うい世界であると、原初史物語作者は感じていたのかもしれない。
ここで原初史物語の作者は、人間は共同性・共生性を求めるに当たって、まずは〈動物〉の中に求めたと語ったが、このことは〈動物〉との共同・共生が消滅してゆくことに危ういものを感じ取っていた、その原初史物語作者の危機意識がここに示されたということではないか。
ここの物語をこのように生態論的観点からの社会批判として読むのはもちろんわたくしの推測の域を越えるものではないが、こう読むのも面白いことではないかとおもっている。
さて、ここで、〈人間が動物に名を付ける〉ということが語られている。ここで語られていることは何であろうか。まずそれを語るときの原初史物語の言い方に留意したい。
その言い方は〈主なる神は動物を人のところに持って来て、人がどう呼ぶかを見ておられた〉であるが、そうすると人間が動物に名を付けることは神ヤハウェのうながすところであったということになる。そうであるとすると、ここは次のことを意味することになる。
〈人間が動物に名を付ける〉ということは、〈人間が動物との共同・共生の関係を持つことを始めた〉ということを示している。動物を創造したのは神ヤハウェであるが、この動物との関係をつくるそのことは〈神が人間に委託した〉ことである、このことがここで言われていることではないかとおもわれる。
この〈人間が動物に名を付ける〉であるが、これは人間の動物に対する支配を意味するものではない。そうではなく、人間が動物に対し人間の責任において関係をつくってゆくことを意味する。人間と動物との関係のありようについては、神ヤハウェが人間に委託した事柄であるということ、それがここで言われていることであるとおもわれる。
人間の動物に対する責任についてはすでに創世記1章の終わりのところで述べられている(1章29~30)。すなわち、食べ物の公平な分配調整、人間が動物の分まで取ってしまうことのないように、動物の分はそれとして確保するように、これが人間の動物に対する責任であり、ここから人間と動物との共同・共生の関係が始まる、創世記一章の終わりのところで述べられていることは、このことである。
さて、創世記の原初史物語作者は、人間は共同性・共生性を持つ存在として創造されたと語り、人間はその共同性・共生性を動物との関わりの中に求めたと語ったが、この語りを入れてからであるが、原初史物語の作者はこの動物の中において〈自分に合う助ける者〉に出会うことはできなかったと語る。本文をいまいちど掲げると、
2章20
「人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名を付けたが、自分に合う助ける者は見つけることができなかった。」
ここで言われている〈自分に合う助ける者〉とはどのような者のことであろうか。これを解するため、ここで〈合う〉という言葉に訳されている、そこのところで意味されていることを探っておかなければならない。
ここはこう言ってよいかとおもう。すなわち、この〈合う〉という言葉に訳されているここは〈自分の真向かいに居て向き合う〉という意味である。そう解してよいとすれば、〈助ける者〉とは〈自分の真向かいに居て向き合う者〉のことと言ってよいだろう。原初史物語の作者は、人間はこの意味における〈助ける者〉に出会うことは動物の中においてなかった、と語る。
物語作者は、こう語った後、次のように語る。
2章21
「主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉でふさがれた。」
ここのところについての説明として最適の文献は、たびたび挙げるが、月本昭男の『創世記Ⅰ』である。そこにしるされているところを紹介する。
相互性に支えられた対等な他者(「汝」)は、結局、外部から与えられるものではなかった。まず、自らが裂かれる必要があった。神ヤハウェは人間に「深い眠り」を下し、その肋骨一本を取り出して、それをもって「つれあう助け」を造る。「深い眠り」とは人間の自己意識が消滅し、神の意思が顕わされる状態のことである(創15章12、サム上26章12、ヨブ4章13など)。「汝」としての対等な他者との出会いは、人間の自らの胸が裂かれ、自らが一旦死んで生まれ替わることと不可分である。
ここの月本昭男の解説は適切である。原初史物語作者によれば、〈自分に合う助ける者〉、すなわち人間が共同性・共生性を得てそれを確認することのできる対象相手は〈自分の胸が裂かれ、自分の胸から造り出されるもの〉である。こう述べる月本昭男の『創世記Ⅰ』の解説は適切である。
ここで留意が必要である。原初史物語作者は、ここで、人間としての共同性・共生性を確認できた対象相手は〈自分の胸が裂かれ、自分の胸から造り出されたもの〉においてであるとしたが、この後すぐに、人間はこの対象相手を棄てることをするということを描く(それはこの後の三章の物語において)。そうすると、ここ二章二一の美しい語りは、三章の物語においてしるされている悲惨な物語展開のために敷いた伏線であると言えそうである。
この後に続く原初史物語の語りはこうなっている。
2章22~23
「そして、人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れて来られると、人は言った。『ついに、これこそ、わたしの骨の骨、わたしの肉の肉。これをこそ、女(イシャー)と呼ぼう、まさに、男(イシュ)から取られたものだから。』」
ここは〈自分に合う助ける者〉が〈神ヤハウェによって創造された〉ということが語られているところである。そして、ここには〈自分に合う助ける者〉は〈男〉にとっては〈女〉であり、〈女〉にとっては〈男〉であると述べられている。そしてさらに、ここには〈自分に合う助ける者〉として〈男〉と〈女〉はまったく対等な関係にあるとして述べられている。
さて、この後に続く物語の文章はこうなっている。
2章24
「こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。」
この箇所について参照されるべき重要な文献は、ここでも挙げるが、月本昭男の『創世記Ⅰ』である。そこにしるされているところを紹介する。
「男は父母を離れて」の「離れて」のところであるが、この語「アーザブ」は「見放す」という意味の動詞である。たとえば、「わが神、わが神、どうしてわたしを見棄てられるのですか」(詩22篇2)。ここで言われていることは、夫は彼の父母をうちやってまでして、妻と結びつく。夫と妻の関係は親と子のそれにまさるということである。
こういう見方は個人主義の今日の社会においてはさほどの抵抗感はないかもしれないが、家父長制が支配的な古代イスラエル時代にこれがしるされたことに思いをいたすならば、この記述は当時の一般社会通念に対する批判であったとみてよい。
古代イスラエルの富裕層においては婚姻の慣習として一夫多妻が一般的であった。それに対して、ここでは一夫一妻の立場が実質的に表明されている。夫妻の関係の方が親子の関係にまさるという表明は、父系家族共同体の存続が至上命題とされ、子を生む女性はそのための手段とみなされかねなかった家父長制社会を非本来的なものとして浮かび上がらせずにはおかなかったであろう。
この月本昭男の解説は適切であり重要である。原初史物語の創世記2章24の〈男は父母を棄てて女と結ばれ、二人は一体となる〉では〈家父長制〉に対する否が語られていると言うことができる。〈父母を棄てて〉は家父長制の解体を意味する。また、この創世記2章24の「男は女と結ばれ、二人は一体となる」で実質的に意味されていることは〈一夫一妻〉であるゆえ、ここには〈一夫多妻〉に対する否が語られていると言うことができる。ここの月本昭男の『創世記Ⅰ』における解説は適切である。
そうすると、この創世記2章24において言い表されている主張は、創世記の原初史物語が意図しているダビデ・ソロモン王政に対する批判、それをここでもおこなっているとみることができるのではないか。ダビデ・ソロモンの王政は〈家父長制〉であり、〈一夫多妻〉の典型である。創世記2章24において言い表されている主張は、このダビデ・ソロモン王政に対する批判であるとみることができるのではないか。わたくしはここをそう読む。
創世記の原初史物語作者は2章24の語りにおいても、時代と社会に対する批判を述べている。その批判は物語に託してという方法、すなわち〈隠喩〉の方法による。そうなっているのは、物語作者の批判が強大な権力に対する批判であるからである。
ここで、一つの留意を述べておきたい。それは、創世記の原初史物語の持っている〈時代史的制限〉ということについてである。
この創世記の原初史物語作者は、〈人間はその共同性・共生性を求め、それを男と女の関係において見出し(2章22)、それを夫と妻の関係において得るとしている(2章24)〉のであるが、これは時代史的制限の中にある記述としておさえておきたい。
創世記のここの記述を、〈時代を越えて通用するただ一つのありようであるとすること〉は適切ではない、と、わたくしは考える。というのは、人間が共同性・共生性を求め、それを見出し、そしてそれを得る、それは創世記の原初史物語の語っているところに限定されるものではなく、ここに示されているのは一つのモデルであり、一つのモデルにすぎないということを認める必要があるからである。
人間が共同性・共生性を求め、それを見出し、それを得ることができる対象・場所・環境は多様であってよいし、そうあることが望ましいし、その多様性を生み出してゆくことが今日の課題である、と、わたくしは考えている。
ここで、いまいちど確認する。創世記の原初史物語が人間の共同性・共生性を確認するべき対象・場所・環境を〈男と女〉の〈一夫一妻〉にあるとしたここの物語は、〈一夫多妻〉の富裕層に対する批判、とりわけ〈一夫多妻〉のダビデ・ソロモン王政に対する批判を意図したものである。また、〈男は父母を棄てて女と結ばれ、二人は一体となる〉と語るここの物語は家父長制を解体することになるゆえ、家父長制に立っているダビデ・ソロモン王政に対する批判を意図したものである。わたくしにはそうおもわれる。
ここで、この〈創世記2章24〉に関連する新約聖書箇所を挙げる。
まず、マタイ福音書23章9をみておきたい。そこにはイエスの言葉がしるされている。「地上の者を『父』と呼んではならない。あなたがたの父は天の父だけだ。」ここでイエスは〈父〉という呼び名を〈神〉にのみ帰し、それ以外に父という呼び名を用いてはならないと言っておられる。
次に、マルコ福音書10章30をみておきたい。そこにはイエスの共同体に属する者たちについて述べられているのだが、そこで挙げられる者の中に〈父〉と呼ばれる者はいない。つまり、イエスの共同体には〈父〉と呼ばれる者は存在しない。実際には子を持つ父はいたであろうが、〈父〉の呼び名はこのイエスの共同体において出されることはなかった。
これらの箇所から推定されることは、新約聖書の時代の最初期キリスト教の人々は〈家父長制〉を認めていなかった、これに対し否を言っていたということ、これが推定され得る。新約聖書の時代の最初期キリスト教の人々は社会に対し批判を持ち、自分たちの共同体が社会に対し引くべき一線について心得ており、これについての注意を怠ることのないようにしていた、と言ってよいとおもう。
ここで、この〈家父長制〉の問題はこの国日本社会の問題であることを確認しておきたい。
この国日本には〈天皇制〉という〈家父長制〉があり、これが問題である。ここで問題である理由を述べておきたい。〈家父長制〉は〈民族主義エゴイズム〉と親和的体質にある。家父長制が民族主義エゴイズムに常になるということではない、しかし、そうなる親和性を持つ。また、〈家父長制〉は〈国家主義エゴイズム〉と親和的体質にある。家父長制が国家主義エゴイズムに常になるということではない、しかし、そうなる親和性を持つ。〈天皇制〉という〈家父長制〉は歴史の実態からみてみると、この国日本を民族主義エゴイズムに、そして国家主義エゴイズムに駆り立て、極めて悲惨な結果をきたらせた。
創世記の原初史物語によれば、人間は共同性・共生性を持った存在としてあり、人間は共同性・共生性を確認する対象相手を求めるとあり、この原初史物語の言うところは適切であるが、問題はそれを何処に求めるかである。それを〈家父長制〉の中に求めるとき、これに親和的である〈民族主義エゴイズム〉〈国家主義エゴイズム〉の流れに取り込まれる。それを〈天皇制〉という〈家父長制〉の中で経験したのがこの国日本社会にいる者たちである。このことを経験した歴史をこの国日本にある者は忘却してはならない。
さて、2章の物語の結びは次のようになっている。
2章25
「人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。」
この2章25の「人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった」は〈土で造られている〉ことを恥ずかしいこととはしなかったということ、〈もろい〉〈よわい〉者であることを恥ずかしいこととはしなかったということ、つまり、互いに〈もろさ〉〈よわさ〉のありのままを受け入れ合っているということ、その仕方で共同・共生が成り立っていたということ、2章25のこの文章はそれを物語るものと言ってよい。
この語りは文脈から言うと、これから展開される物語の準備として置かれている。この後にしるされる3章の物語には、人が自分の裸を恥じるに至ったとある。ここはそのために敷かれた伏線である。
人間が自分の裸を恥じるとは、どういうことを言っていることか。このことについてはすでに述べたが、いまいちど確認すると、それは〈土で造られている〉ことを恥じるということ、〈土で造られている〉ということは土の性質である〈もろさ〉〈よわさ〉を持つということ、ここで言われている〈自分の裸を恥じる〉とは〈もろい〉〈よわい〉者であることを恥じるということ、それを意味している。
この後の3章にしるされる物語によれば、〈自分の裸を恥じる〉つまり〈土〉の性質である〈もろい〉〈よわい〉を恥じる、結果は成り立っていた〈もろさとよわさのありのままを受け入れ合う〉共同・共生が壊れる、そのようになったのには原因があってその原因は〈善と悪を知る知識の木〉の実を食べたことによる、〈善と悪を知る知識の木〉の実を食べるとこれほどに大きな問題が生じる、原初史物語の作者はこう語るのである。そうすると、
この2章25の〈二人は裸であったが恥ずかしいとはおもわなかった〉の語りは、〈善と悪を知る知識の木の実を食べる〉それをしないでいた前のときと、それをしてしまった後のときとではこれほどに相違することが生じる、それを浮き彫りにするために敷いた伏線であったと言ってよいとおもう。