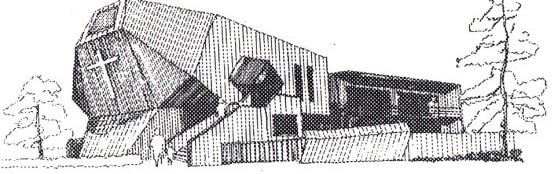[委託]
1章11~13
「神は言われた。『地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持
つ実をつける果樹を、地に芽生えさせよ。』そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見て、良しとされた。夕べがあり、朝があった。第三の日である。」
ここには天と地の創造の三日目のこととして、「種を持つ草」「種を持つ実をつける果樹」が創造されたとある。ここで、それが何を意味するか探ることにする。
創世記1章の天と地の創造物語の終わりの29節と30節にはこうしるさ
れている。
「神は言われた。『見よ、全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。』そのようになった。」
ここには「食べ物」のことが言われている。「種をつける草」と「種をつける果実のなる木」は「あなたがた」すなわち人のための食べ物、「あらゆる青草」(これは「種を持たない草」のこと)は「獣」「鳥」「這うもの」すなわち人を除く全ての命あるものの食べ物としるされている。
1章11と12では「種をつける草と木」のことしか述べられていないが、ここは1章29と30において述べられていること、すなわち神の創造した命ある全てのものの「食べ物」を芽生えさせること、それが地に命じられたことである、と読むのがよいとおもわれる。
ここで、注意して読んでみると次のことに気付かされる。それは、「種をつける草と木」これが造られるとき、他のもの(生きもの)が造られるときと違いがあるということ、そのことに気付かされる。
11と12節のしるすところによると、「食べ物」は神が地に命じて、地がそれを芽生えさせるとなっている。すなわち、「食べ物」は神が直接造るのではなく、神が地に命じて、地が産み出すとなっている。つまり、「地」というものが「命」の継続に関し使命を委託されているということ、これが言われている。
ここには古代オリエントの観念の「母なる大地」が用いられているとおもわれる。この「母なる大地」の観念は自然を神にする道に通じており、偶像崇拝を産み出す温床となるものである。創世記の原初史物語の作者がこの観念を肯定し承認して受け入れているはずはない。ではなにゆえ、この観念が用いられたのかを問うておくと、
ここで原初史物語の作者が述べていることは、神は地に使命を与えたということ、それは植物を産み出す使命を与えたということ、この植物は神によって創造された命あるものの「食べ物」のことであるからして、神は地に「食べ物」を産み出すという使命を与えたということである。
つまり、「食べ物」については神が直接造るのではなく、神が地に委託する形で、地がその与えられた使命に応えてそれを産み出すという形を取るということ、こういうことがここで言われていることである。原初史物語の作者が古代オリエントの観念「母なる大地」を用いたのは、これを言うためであったとおもわれる。
「地」は「命」を「創造」することはできない、それができるのは神のみであるが、「地」は「命」の「継続」に関し使命を委託されている、これがここで言われていることであるとおもわれる。
ここで注目しておいてよいことがある。原初史物語の作者は、神は「食べ物」に関し配慮をしたと語ったが、その「食べ物」についての配慮を神は天と地の創造の三日目におこなったと語った。原初史物語作者は、神が生きとし生けるもの全てのための「食べ物」の配慮をしたのは天と地の創造の「三日目」という時間の順序、この優先順位においてであったと語った。この原初史物語作者の語りに注目があってよいとおもう。
ここで、この1章11と12が持つ文脈をおさえておきたい。この11節と12節は4章にしるされている物語のための道備えの文脈の中に置かれていると解される。
創世記4章には地が食べ物を産むことができなくなるということがしるされている。そこには地が食べ物を産むことができなくなる原因について述べられている。
兄のカインが弟アベルを殺すということが起こる。そのとき流されたアベルの血が大地に流され、注がれることになる。地が食べ物を産むことができなくなる原因はこれであると述べられている。
4章12にこうしるされている。「土を耕しても、土はもはやお前のために作物を産み出すことはない。」ここで「お前」と言われているのはカインのことであり、地に血を流し注いでしまった者のことである。
ここで留意したいことは、この創世記4章は特徴を持っているということである。
古代の民話には、地が食べ物を産むことができなくなるとき、人身犠牲がおこなわれるとするものが圧倒的に多い。一例をあげると、雨が長期にわたって降らず旱魃に襲われる、食べ物に窮する、そのとき、自然の神の怒りを招いているとして人々はその神の怒りを鎮めるため人身犠牲をおこなう、そうすると雨が降ってきて旱魃による飢餓から救われる。
この人身犠牲は現代においてもある。わたくしは北海道史の研究家の講演を聞いたことがある。北海道の鉄道を敷くためのトンネルを掘る工事において、地の神の怒りを鎮め安全を確保するため、人身犠牲がおこなわれたという。
創世記4章にしるされているところは、こういった人身犠牲のこととは逆のことである。そこにしるされていることは、殺された人間の血が地に流されると、地は怒って食べ物を産むことを拒否するということ。創世記の原初史物語は語る、殺人が起こりその血が流されるなら、地は神から委託された食べ物を産むことをしない、と。
この創世記の原初史物語の語るところは、今日まさにこの日本における現実である。放射能で汚染された地は「食べ物」を産まない。創世記4章にしるされていることが、今日まさにこの国における現実である。
ここで、このような悪しき状況を招来させている原因の一つを述べておきたい。
人類が近代という時代に入ったとき、近代の支配的価値となったのは科学である。宗教は科学との間で領分を分ける。宗教は人間の精神の問題を扱う、科学は人間の身体の問題を扱う。宗教は科学に口を出さない、科学は宗教に口を出さない。宗教はこのようにすることで近代の科学支配の中で宗教の命脈を保ってきた。
近代において科学は自由に振舞うことになる。科学のハンドルを握るのは人間、ブレーキをかけるのも人間。だが、人間は自由に振舞う科学をコントロールできなくなり、科学は人間から離れて自由に振舞い、科学の一人歩き、いや一人走りとなり、それを止めることができなくなった。今日、この状況にある。キリスト教はこういう状況になっても科学に対し口を出さない、人間の精神の問題にだけ関わる。
創世記の原初史物語の作者は捕囚となっているバビロンにおいて古代オリエントの科学の知恵と技術の最高のものを見、しかし、そこで科学の暴走の様を見たのではないか。創世記の原初史物語の作者はその知見をふまえたうえで、地とは生きとし生けるものの食べ物を産み出す使命にあると語った。このことは、原初史物語の作者が宗教の立場から科学に対し物を申したということ、こう言ってよいのではないか。